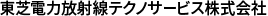放射線を知る
場のサーベイ
場のサーベイとはどのようなことを行うのでしょうか?
これまで3回に分けて原子力・放射線利用分野におけるモニタリングを紹介してきましたが、 「モニタリングとサーベイ」の項で紹介したとおり、放射線施設では放射線管理の一環として、モニタリングに加えて各種のサーベイが行われます。ここでは放射性物質を取り扱う放射線施設において日常的に実施される、場のサーベイについて紹介します。
放射性物質を取り扱う放射線施設では、連続的・継続的に放射線や放射能の量を測定、監視するモニタリングが行われます。しかしながら、モニタリングで使用される機器の多くが固定式であること、設置台数が限られることなどから、個々の作業現場の放射線管理に適した測定とはならないため、個々の作業現場における放射線管理としてサーベイが実施されます。
通常、サーベイはサーベイメータと呼ばれる可搬型の測定機器を用いて実施されます。放射線の量を測定ではNaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータや電離箱式サーベイメータが利用され、放射能の量(表面汚染密度)の測定ではGM管式汚染サーベイメータやプラスチックシンチレーション式汚染サーベイメータが利用されます。なお、表面汚染密度の測定では、多くの場合、スミア法と呼ばれる“ふき取りろ紙”や“ふき取り布”を用いる手法が利用されます。スミア法は、測定対象の表面についてろ紙や布で所定の面積をふき取り、ふき取ったろ紙や布を汚染サーベイメータで測定します。間接的に汚染を測定するため、測定対象周囲のガンマ線によるバックグラウンドが高い場合でも汚染測定が可能になります。
放射能の量(空気中放射能濃度)については、測定対象となる放射性物質がガス状の場合は可搬型のガスモニタを、ダスト状の場合はダストサンプラと汚染サーベイメータの組み合わせにより、測定を行います。
なお、空気中放射能濃度の測定では作業前に比較用データを取得する場合があります。作業現場で行う空気中放射能濃度の測定では、測定対象となる放射性物質の種類によりますが、多くの場合、全アルファ線測定または全ベータ線測定が行われます。しかしながら、通常、空気中には自然起源の放射性物質が含まれるため、全アルファ線測定や全ベータ線測定では、得られた放射能が自然由来によるものか、測定対象によるものか判別できないことから、事前に作業場所における自然起源の放射性物質による影響を把握しておき、作業中の測定結果と比較することで速やかな一次判断ができるよう工夫します。
施設によっては各種サーベイを行うタイミングをルールとして規定している場合もありますが、非密封の放射性物質を取り扱う場合、ルールに寄らず、作業内容やその進捗に応じてサーベイを行う必要が生じます。
このサーベイの目的は、フード等の封じ込め機器や設備が適切に動作していることの確認や、表面汚染密度や空気中放射能濃度が事前計画の通りにコントロールできていることの確認になります。
目に見えない放射性物質の取り扱いでは、作業進捗に合わせたサーベイを適切に行うことによって、放射性物質の取扱いをより安全なものにすることが重要です。
以下に場のサーベイについてサーベイの目的の例を示します。
■ 場のサーベイ 空間線量
| 時期 | 施設 | サーベイの目的例 |
|---|---|---|
| 作業前 | 原子力施設など | ・被ばく線量の推定、遮へいなどの検討など |
| 作業中 | 原子力施設など 研究施設など |
・被ばく線量の推定と実測の比較など ・ベータ線による被ばく線量、遮へい状況の確認など |
| 作業後 | 研究施設など | ・利用した線源の片付け忘れの確認など |
■ 場のサーベイ 表面汚染密度
| 時期 | 施設 | サーベイの目的例 |
|---|---|---|
| 作業前 | 原子力施設など 研究施設など |
・作業場所の汚染状況の事前確認など |
| 作業中 | 原子力施設など | ・除染実施の判断や区画外への汚染の飛散がないことの確認など |
| 作業後 | 研究施設など 研究施設など |
・一時的な汚染区域を解除する際の確認など ・汚染の飛散がないことの確認など |
■ 場のサーベイ 空気中放射能濃度
| 時期 | 施設 | サーベイの目的例 |
|---|---|---|
| 作業前 | 原子力施設など | ・比較用データの取得など |
| 作業中 | 原子力施設など | ・作業中断の判断など |