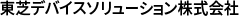- 02
- CONVERSATION
- 役員
インタビュー
モノ作りの『面白い』を見つけよう!
興味を持って、じっくりとひたむきに。
エンジニアとして、ともに成長していこう。
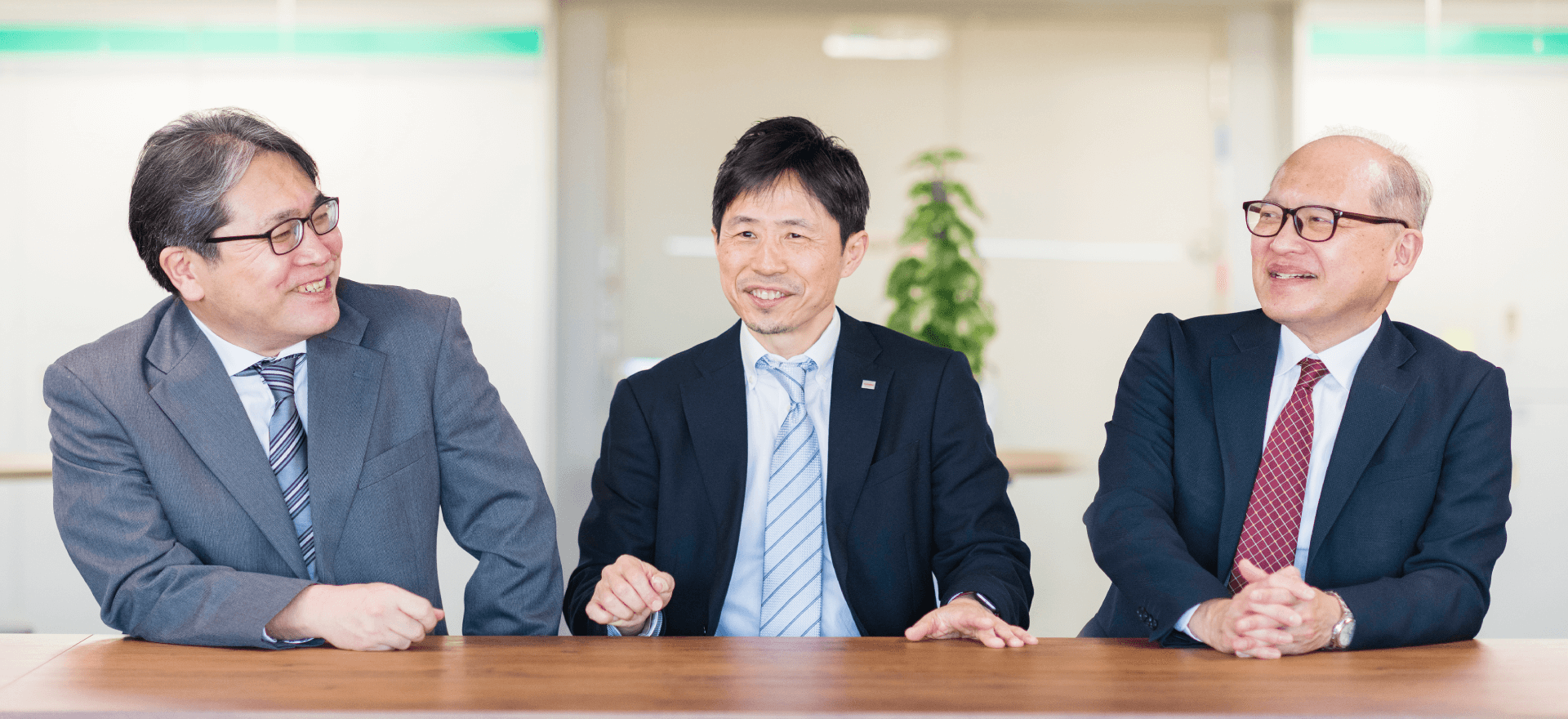
「半導体ってこの先どうなの?」「専門知識は必要なの?」「自分にできることはあるのかな…」こんな疑問を持っている学生の皆さんに、東芝デバイスソリューションの3つの部門担当役員が熱い思いをお伝えします。
東芝半導体の過去・現在・未来と、東芝デバイスソリューションができること
Q:まず、東芝の半導体事業についてお聞かせください。長い歴史を持つだけでなく、現在も業界内で大きな存在感があると感じています。
-
安西:東芝半導体の源流は真空管、さらには電灯(電球)にまでさかのぼります。創業当初から培った技術力やお客様からの信頼を得て関係性が持続し「今」があります。また、東芝半導体事業が一丸となったIDM*1(Integrated Device Manufacturer)というビジネスを行っているため、グループ内で全体最適を見出すことができます。そして、性能や信頼性、供給責任などをトータルで対応できるというのが非常に大きな強みであると考えています。さらに2024年より半導体の開発拠点が小向事業所に集約されました。ここは、もとは東芝の総合研究所でしたので、グループの広い知見や技術が半導体に活用できるとともに、拠点集約によるシナジー効果が大いに期待されます。
*1 IDM(Integrated Device Manufacturer:垂直統合型デバイスメーカー):半導体の設計から製造・組み立て・販売までを一貫して行うこと
-

設計開発統括部 担当役員 安西
吉田:半導体事業においては、IDMに加えて、その領域の広さも大きな強みの一つです。例えば皆さんが日常で使っているスマートフォンやパソコン、家電製品などの身近な機器から、現在注力している車載・産業機器などの領域に東芝半導体が使われています。また、東芝グループとして目指すカーボンニュートラル*2やサーキュラーエコノミー*3の実現にもグループ内の事業体と連携して貢献できるところが、半導体専業会社に無い、総合メーカーだからこその醍醐味です。
*2 カーボンニュートラル:温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること
*3 サーキュラーエコノミー(Circular Economy):「循環型経済」と呼ばれる経済システムを表す言葉。経済活動においてモノやサービスを生み出す段階から、リサイクル・再利用を前提に設計するとともに、できる限り新たな資源の投入量や消費量を抑えることで既存のモノをムダにせず、その価値を最大限に生かす循環型のしくみ
永島:2025年、東芝は創業から150周年を迎えました。この長い歴史の中でいろいろなことをやってきた東芝だからこそいろいろな半導体が必要で、その技術の蓄積は他社に類を見ることはありません。使う側と作る側が同じ会社にいる、顧客がグループ内にいるということも、最先端の半導体を長く作り続けてこられた大きな要因だと感じています。
-
Q:東芝グループの中で、東芝デバイスソリューションはどのような存在なのでしょうか。
吉田:当社はエンジニアリング会社として、東芝半導体事業の中核に深く入り込んでいます。それも一部分だけではなく、企画・設計・開発に至るまでトータルで、です。そもそも当社もIDMに近いスタイルで事業を行っていますが、小回りが利くといった会社の規模感から機動力やシナジーを発揮しやすいといった特長があります。そういった意味で、事業の一体感を持ちながらも瞬発力のあるエンジニアリング会社として、無くてはならない存在になっています。
-
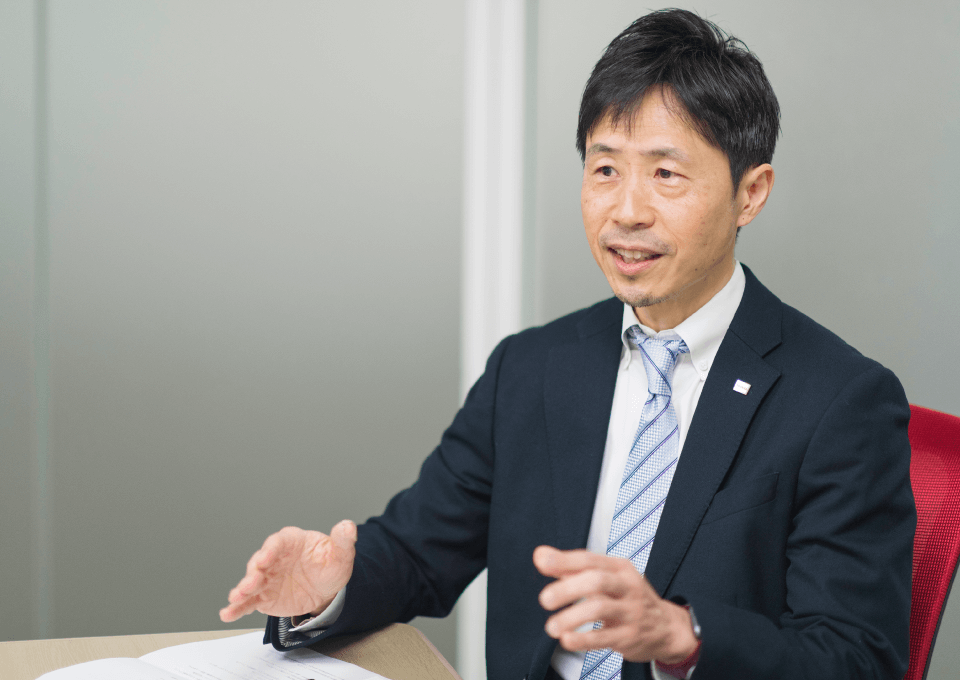
拡販技術統括部 担当役員 吉田
永島:半導体における、あらゆる技術に特化した優秀なエンジニアを育て輩出していますので、当社のリソースが無ければ東芝の半導体事業は成り立たないと言っても過言ではありません。そのくらいグループ内で認知されていますし、社員の皆さんも至るところで実力を発揮しています。
安西:もう一つ付け加えるのであれば、東芝の半導体事業が製品軸で構成されているところ、当社は設立当初から拡販技術部門、設計開発部門、製品技術部門といった機能軸で組織しているということです。専門性の深掘りと効率化の観点から補完・強化するという考えからですが、それが当社の役割であり東芝の半導体事業を信頼性のある強固なものにしていると、グループ内でも浸透していると思います。
-
Q:半導体の未来のために、東芝デバイスソリューションがやるべきことは何でしょう。
永島:半導体は「産業の米」と言われています。既に存在するテクノロジーを支えるだけでなく、あらゆる製品の進歩、これからの便利な社会に無くてはなりません。持続可能な社会を実現するためにも半導体の力は必要ですし、AI(Artificial Intelligence)技術を大きく左右するとも言われています。まさに未来のカギを握っているのが半導体です。そこに我々の知識と経験、技術が生かせるということ、その瞬間に立ち会えるということがとても光栄であり誇らしく思います。
-

製品開発統括部 担当役員 永島
安西:東芝半導体事業部のスローガンは「世界を変える原動力となるのは、いつも私たちの半導体・ストレージであり続けたい」です。まさにたどり着くべきはそこだと思っています。永島さんのお話にもありましたが、これからはAI技術がより一層の進化を遂げるでしょう。ただ、頭脳を支えるためには多くの神経や筋肉が必要で、それが我々の得意かつ注力する分野になります。EV(Electric Vehicle)やロボットも然りで、そういうところに半導体の価値は求められています。その要求に対して、3つの部門によるシナジー効果であらゆる提案ができるのが東芝デバイスソリューションで、社会を変える原動力になり得る会社です。
吉田:お客様と接する最前線の拡販技術部門がマーケットセンサー役(市場の動きやニーズをいち早く察知し、社内に伝える役割)になり、まず世の中の流れがどうなるかをしっかり把握し、お客様が描く未来を共有し、どのような課題を解決しようとしているのか確認することが重要です。そして、それらをタイムリーに製品企画につなげ、設計、開発を行って・・・そういうサイクルをしっかりと回していくということですよね。
安西:部門が連携することで、お客様が考えている「価値」を製品として具現化できるのが当社であり、それは機能軸で組織されているからこそできるのだと思います。
東芝デバイスソリューションにはこんな人が必要だ!
Q:それぞれの部門の特長と、どんな人材が必要なのかを教えてください。
吉田:拡販技術部門は、東芝半導体を拡販するために、アプリケーション技術、ソリューション技術といった側面からさまざまなサポートを行う部門です。さきほど、マーケットセンサーというワードを出しましたが、最前線でお客様と直接会話をするのがアプリケーション技術のメンバーです。お客様が抱える課題や、言葉に出てこない「思い」を敏感に察知し、東芝半導体を用いたソリューションで課題解決や価値提案を行うことが主なミッションとなります。ソリューション技術は半導体を効果的に使用するための各種シミュレーションデータの準備や実動作で機能を確認できるデモセットなどを開発し、拡販活動をサポートします。 どちらも最も必要とされるのはコミュニケーションで、自ら考え行動する力とチャレンジ精神です。いまは世の中の変化が早く、今日までの常識はすぐに陳腐化してしまいます。変化を恐れず、何事にも前向きに立ち向かっていく、そういうエネルギーが必要です。
安西:設計開発部門は、デジタル、アナログ、ディスクリートといった各半導体の回路設計やレイアウト設計を行っています。次々に新しい製品に取り組みますので、そこには大変な苦労もありますが、完成した時の達成感はその上をいくものです。何事にも興味を持つ人であれば、ワクワク楽しみながら取り組むことができる仕事です。回路設計と聞くとほとんどの人が「難しそう」と感じると思います。でも私は、回路設計者はサーキットデザイナーと訳されるように、設計者はデザイナーだと思っているんです。良い回路は本当に美しいと。持論ですが(笑)。電気・電子のバックボーンが無くても、自分の意外なセンスや才能を発見・発揮できるかもしれません。
永島:製品技術部門は、開発が計画どおりに進むように指揮をとり、コスト管理やスケジュールのフォローを行う製品開発・評価、製品が市場に出る前の品質をチェックする半導体テスト、万が一製品に不具合があった場合の原因を追究し改善を見出す半導体解析の3つのチームで構成されています。生産効率を上げるということは利益を得るための企業の重要なミッションですが、同時に品質の向上も必要不可欠です。いかにしてテストを効率よく行い同時に品質も上げるという、相反する作業が求められるチャレンジングな面白い部門です。そうした意識をもってモノ作りを楽しみたい人にはピッタリだと思います。
Q:新入社員への教育やキャリアプランなどはどのように取り組んでいますか?
安西:1~2年前から、部門ごとではなく全社で新入社員を育てるという体制になっています。内容に応じて主催部門を決め、全員を集めて専門技術教育を行うといったスタイルです。
永島:そういった意味では、新人さん同士が部門を超えてごく自然に仲良しになりますので、こちらが意識しなくてもすすんで交流してくれるというか(笑)。後々の業務にも良い影響が出るのではないかと期待しています。
吉田:一般教育以外では、入社後に所属部門で役割が与えられたときに、「スキルチェックシート」というかたちで、業務分野ごとに具体的なスキルや力量の目標を決め、その結果を毎年上長と面談しながら評価します。技術教育で足りないところはメンターに聞いたり、OJTで学んだりといった取り組みです。ここで重要なのは、「具体的に何ができるようになって欲しいか」という期待値をひとり一人明確にして共有し、どの程度できたのか、どういうところがダメだったのかをお互いに認識して見直しを行うことです。PDCA*4を回すイメージですね。そうすることで、1年間でどこが成長したのかが見えるようになり、キャリアアップにもつながっていきます。
*4 PDCA:Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)を繰り返すことで、業務を継続的に改善していくためのフレームワーク
安西:どの部門でも専門性のさらなる強化と事業・製品経験を補うため、親会社への実習は積極的に行っています。何事も経験してもらい、適性を見極め、自分のやりたいことを極めてもらいたいという考えからです。設計開発部門では、デジタル、アナログ、レイアウト、と半年程度かけて新入社員の方にローテーションしてもらいます。自分は何をやりたいのか、何を頑張れるかが、そこである程度見えてくると思うのです。同じような考えで部門を超えての異動も積極的に受け付けています。
永島:安西さんから実習のお話がありましたが、製品技術部門では、量産現場である工場での実習を行っています。半導体テスト開発に従事する私たちにとって、現場で実際のテスト工程を経験することは非常に重要で意味があります。工場は24時間稼働ですから3交代勤務を2カ月経験してもらいます。実習を終えて戻ってくると皆さんがとても成長しているのを実感します。製品が作られお客様のもとへ出荷されるという製造の「現場」を見ることで、社会人としての自覚と自信が身につくのだと思います。
Q:学生の皆さんにお伝えしたいことがありましたらお願いします。
安西:学生の皆さんは必要なスキルを気にされているかと思いますが、知識や技術は会社に入ってから学んでもらえば問題ありません。夢中になれるということが大事です。やり抜く力、聞く力、伝える力を持っていれば言うことなしです。
永島:何事も基本はコミュニケーションです。口下手でも気にすることはありません。今の時代、伝える手段はたくさんあります。
吉田:焦らずゆっくりと進みましょう。いま私が懸念しているのは、早く結果を求める人が多いのかな、ということです。先ほど「目標やテーマを決めて…」という話をしましたが、その部分も含めて、方向を変えてみたり考え方を変えてみたり、じっくりと腰を据えて自分の「大きな可能性」を探してください。

Q:最後に、東芝デバイスソリューションの魅力をお願いします。
永島:東芝半導体事業の屋台骨と言っていいくらい、技術に特化したエンジニアが揃った会社です。会社としてはコンパクトですが、ポジションは重要、無くてはならない存在です。また、野球やラグビーの応援など東芝グループ会社としての楽しみ方もあります。コンパクト+スケールの大きさが、居心地抜群です。
安西:部門間の垣根も低いですし、一体感満載です。技術を身につけ手に職を持ったスペシャリストが集まったエンジニアリング会社です。それが当社の強みであり、全社員がそういう意識をもって半導体の未来を支えて行けたらと考えています。
吉田:東芝グループの一員という大きな枠組みの中で、半導体事業を一気通貫でできるのがすごいことです。幅広くいろんなことができる、小回りが利く、機動力がある…何よりチャレンジできるステージが用意されているのが一番の魅力です。
本日は貴重なお話をありがとうございました。
-
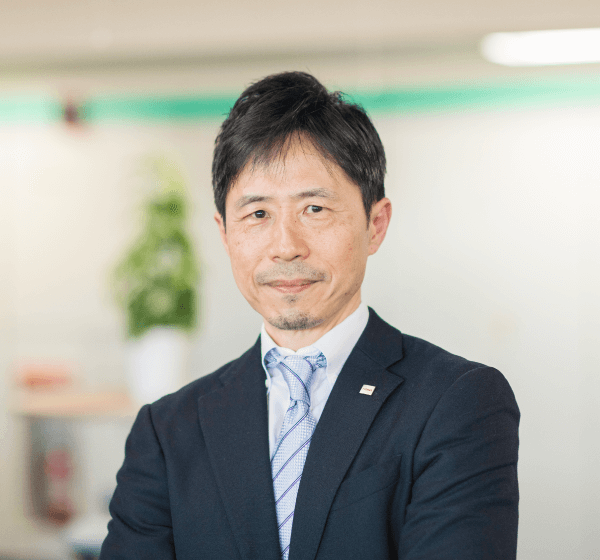
拡販技術統括部 担当役員
吉田 満
1989年入社
ソフトウエア開発エンジニア、応用技術等を経て現職。
座右の銘は「満は損を招き、謙のみ福をうく」。
謙虚で人から常に学ぶ姿勢でいること、それが重要。 -
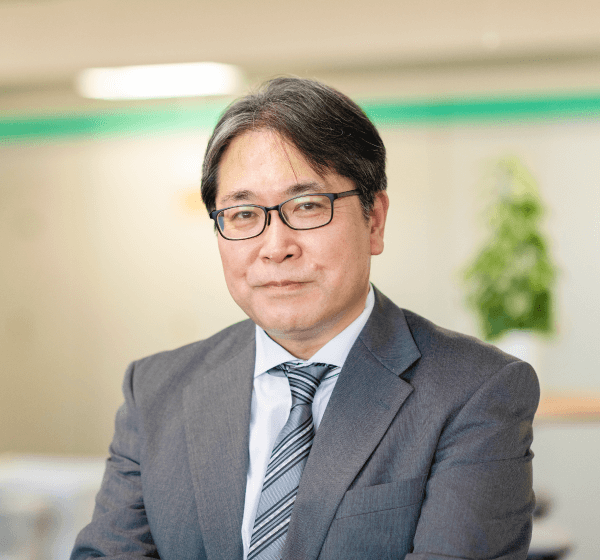
設計開発統括部 担当役員
安西 俊一
1989年入社
アナログ設計エンジニアを経て現職。
座右の銘は「急がば回れ」。
遠回りをせよという解釈ではなく、急ぐのであればその間に小さく早く多く回れ。小さな仮説検証をたくさん回して大きな成功をつかみましょう。 -

製品開発統括部 担当役員
永島 彰
1992年入社
テストエンジニアを経て現職。
座右の銘は「技術者とは?簡単に出来ないと言わない人」。
出来ないことが出来るようになるという事は技術者冥利に尽きます。難題には燃えます。